小学4年生の頃だっただろうか。
通知表の先生の欄に「協調性が不足しています」と書かれることが多くなった。
自分ではまったくそのような覚えもなく、意味もわからないまま、それでも歳を重ねていった。
ちょうどこの頃から、クラス内では自然と「仲良しグループ」ができはじめ、子どもたちもそれぞれの個性が現れ出す時期だった。
私は特に意識することもなく話の合う友人たちとつるんでいたが、その中でも変なあだ名をつけたり、冗談と称して物理的に小突いてきたりする者が出てきた。
消しゴムはどこかへ飛ばされ、ノートには落書きがされる。
上履きが隠されることも頻繁だった。
嫌だと思いながらも、孤立することがもっと怖くて、そのグループに残り続けたのだと思う。
自分一人で何もできない人間だったのかもしれない。
今なら、あれは明らかにいじめだと断言できる。
当時も母に話していたはずだが、何も変わらなかった。
母で止まったのか、学校で止まったのか、それさえもわからない。
ただ、どこにも助けはなかった。
それでも学校に通い続けたのは、家にいると父の怒りがもっと怖かったからだ。
学校での嫌がらせよりも、父の拳の方がずっと痛く、恐ろしかった。
思春期に差し掛かるころには、私の心の殻はどんどん固くなっていったと思う。
学芸会ではセリフの少ない脇役ばかりを選び、人前に立つのも苦手なままだった。
買い物も一人ではできず、知らない人に話しかけることも恐ろしかった。
ただ、走ることだけが私にとってポジティブだった。速く走れる自信があったからだ。
速くなるためというよりも「楽しい」から、放課後や休日には一人で黙々と走り込んでいた。
そしてそれが結果を生み、市の大会でいつも上位に入ることができた。
走ることだけが、無意識でできる唯一の自信だった。
部活動はバスケットボール部に入部した。
選んだというより、兄がやっていたからお前もやれと言う父の言葉と、陸上部というものがなかったから。
運動部の中で一番走り込みを行いそうな部。
走り込みは楽しかったけれどバスケットが好きになることはなかった。
レギュラーが取れなくても悔しいという感情は全くなかった。
反抗期に入ると、父の暴力はさらに激しくなった。
私が何に対しても苛立ち、態度が悪くなっていたこともあって、父はよりエキサイトするようになったのだろう。
私が部屋に逃げ込むと呼び出され、無視すると無理やり引っ張り出された。
父は酒癖が悪く、酔うと昔話を繰り返しては、必ずネガティブな話を持ち出した。
そして一度怒ったことをまた蒸し返し、同じように怒る。
これが毎日続く。
こんな理不尽なことが他の家でもあるのだろうか?それともこれはうちだけなのか?と、怒られている間、何度も頭の中で問い続けていた。
兄弟や母も例外ではなかった。
父は彼らにも容赦なく、時には怒鳴り散らし、茶碗や皿が飛び、お米や料理がぐちゃぐちゃに散らばることさえあった。
あの日の光景は、今でも鮮明に覚えている。
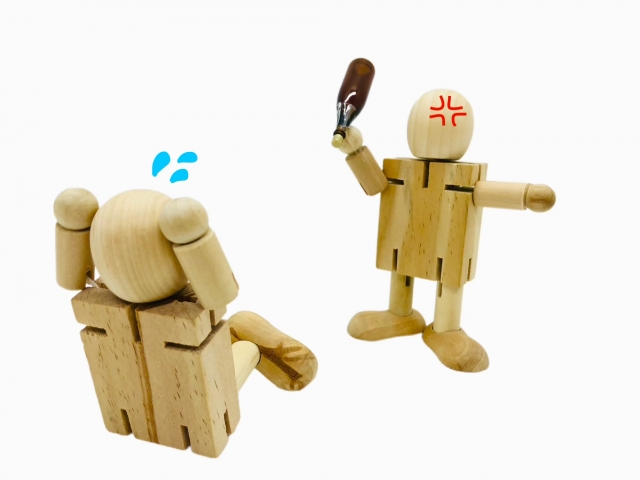
まだ小学生でお酒の味も知らない私だったが、「こんな人間にはなりたくない」と強く思った。
そして、絶対に酒に溺れてはならないと固く心に誓ったのだった。



コメント